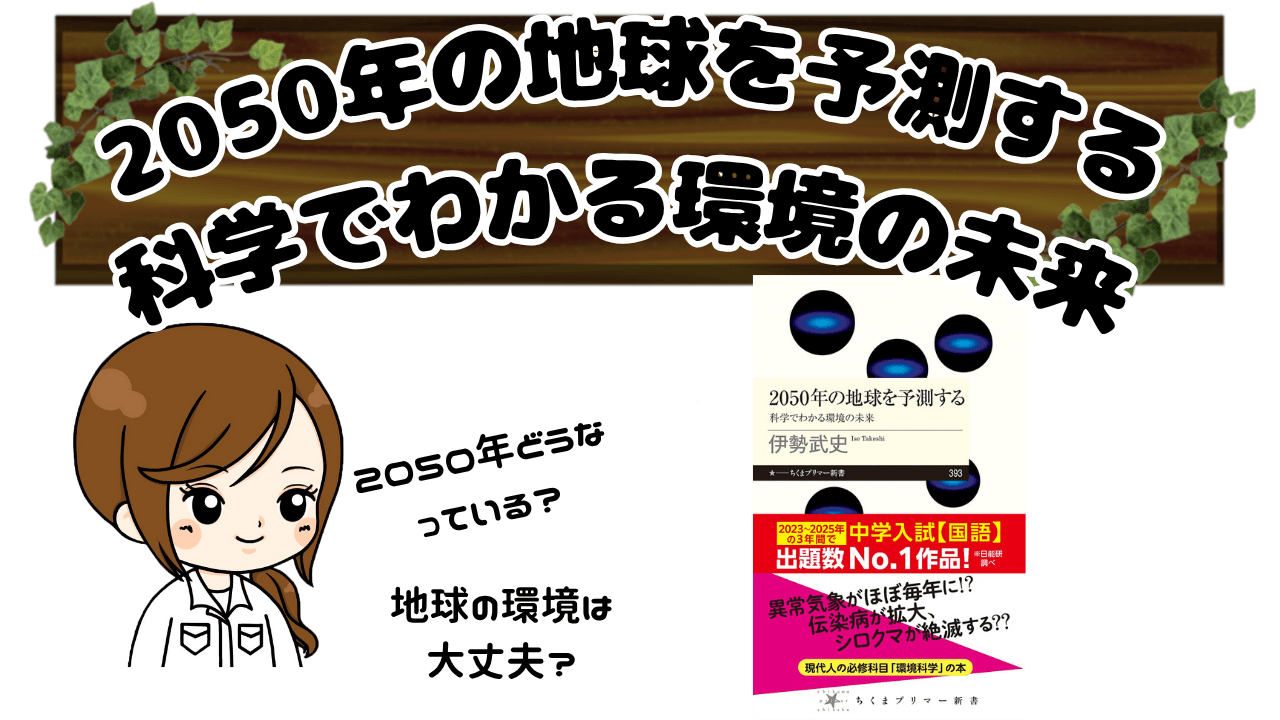
中学受験の大定番!『2050年の地球を予測する 科学でわかる環境の未来』(伊勢武史)を紹介【2025年度頻出】
環境問題は毎年のように中学受験で問われる重要テーマです。
その中でも伊勢武史先生の『2050年の地球を予測する 科学でわかる環境の未来』は、多くの学校で2025年度の入試でも出題されており、環境分野の理解に欠かせない一冊となっています。
この記事では、本書の内容と受験での活用法を詳しくご紹介します。
[product=9784480684189]
なぜ中学受験で頻出なのか?
① 環境問題は「社会」だけでなく「国語」の題材にも
環境問題は社会の知識問題に限らず、国語の説明文・評論文としても頻出です。
この本では、
- 地球温暖化
- 生物多様性の減少
- 再生可能エネルギー
- 環境政策と未来予測
といった受験でも問われるテーマを、科学的な根拠に基づき平易に解説しています。
② 将来の社会に必要な「科学的思考力」を養える
著者の伊勢武史先生は京都大学の准教授で、科学的データに基づいて**「これからの地球をどう守るか」**をわかりやすく解説。
単なる知識暗記ではなく、「考える力」を伸ばす教材としても最適です。
2025年度入試での出題例
2025年の中学入試でも、複数校の国語において本文引用が出題されました。
出題例
- 巣鴨, 大妻, 海陽, 滝・・・
受験生の声:「事前に読んでいたので、背景知識が役に立った!」
どう活用すればいい?
- 親子で一緒に読む(難しい部分は大人がフォロー)
- 内容を要約する練習(説明文対策に効果的)
- 時事問題やニュースと結びつける(最新の出来事とリンク)
特に**「自分の意見を述べる練習」**に最適な内容が多く、面接対策にも活用できます。
用語解説:『2050年の地球を予測する』を読む前に知っておきたいキーワード
フィードバック
ある変化が、さらにその変化を強めたり弱めたりする仕組み。
たとえば、
- 二酸化炭素が増える
- → 地球の温度が上がる
- → 雪や氷が溶ける
- → 地表が黒っぽくなって太陽の光を吸収しやすくなる
- → さらに温度が上がる
このように変化がどんどん大きくなることを**「正のフィードバック」**といいます。
信頼区間(統計学)
データの「だいたいこのくらい」という範囲。
たとえば、「この気温上昇は将来90%の確率で〇〜〇度の間になる」といった予測の幅を示します。
未来の環境を予測するには、この信頼区間の考え方がとても重要です。
パッシブセーフティとアクティブセーフティ
安全を守る2つの方法。
- アクティブセーフティ:事故を起こさないようにする(例:ブレーキ、ABS)
- パッシブセーフティ:事故が起きたとき被害を減らす(例:エアバッグ、シートベルト)
環境問題でも**「起こさない工夫」と「起きたときの被害軽減」**の両方が考えられます。
トレードオフ
何かを得ると、別の何かを失う関係。
- 例:
どじょうが餌を探す → たくさん餌を得られるが敵に見つかりやすい
慎重などじょう → 餌を逃すが敵に見つかりにくい
環境対策でも便利さとコストのバランスなど、トレードオフがよく登場します。
ジオエンジニアリング
地球の気候を人間の手で大きく変える技術。
- 例:宇宙にアルミ箔をまいて太陽の光をさえぎり、温暖化を防ぐというアイデア。
ただし、思わぬ副作用や倫理的な問題もあるため、慎重な議論が必要です。
分散投資とリスクヘッジ
リスクを減らす工夫。
- 分散投資:お金をいくつかの違う場所に分けて投資する
- → どれかが失敗しても、全部がダメになるのを防ぐ
環境政策でも、さまざまな対策を組み合わせることでリスクを下げることができます。
風力発電のバードストライク
風力発電の羽根に鳥がぶつかる事故のこと。
環境にやさしいエネルギーでも、思わぬ悪影響があるため、場所やデザインを工夫する必要があります。
批判的思考(クリティカルシンキング)
情報をうのみにせず、「本当に正しい?」と考える力。
未来の環境問題についても、**「これは本当に正しい予測か?」「別の考え方はないか?」**と自分で考える姿勢が大切です。
まとめ
『2050年の地球を予測する』は、環境問題の基礎と未来を考える視点を身につけられる良書です。
2026年度以降の中学入試でも引き続き重要なテーマとなることが予想されます。
早めに読んで、「知っている」を「考えられる」にレベルアップしましょう!
ツールネット
こちらの記事はツールネットで作成した記事です。
記事提供いただける方、募集中です。
興味のある方はご連絡ください。
© 2021 ツールネット. All Rights Reserved.
